- ホーム
- 学科共通科目
- 授業ピックアップ
授業ピックアップ
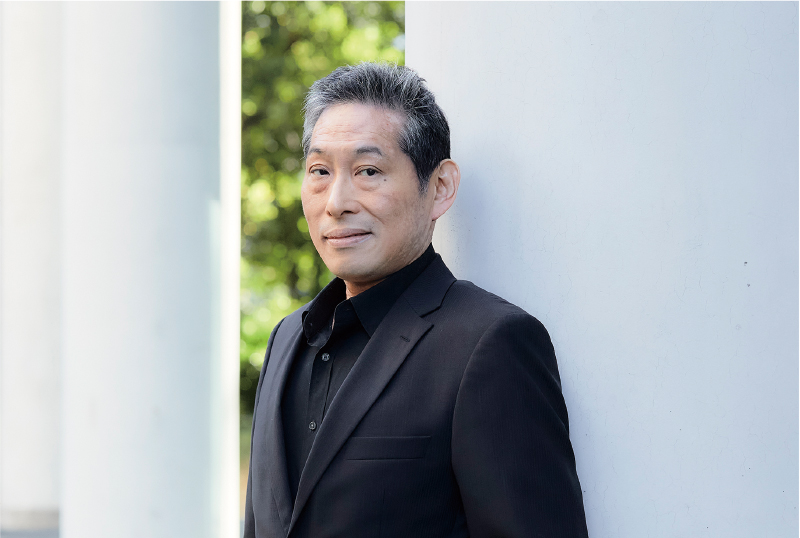
法学部 教授(ドイツ語)
許 光俊
法学部に入学したら、法律や政治に関する専門科目を学ぶのは当然のことです。しかし、それ以外にもたくさんの授業があります。文学、哲学、芸術、物理学、天文学・・・どうしてそんなに多くのことを学ばなければならないのか、若い人たちにはピンと来ないかもしれません。しかし、「やっぱりいろんなことを知っていなくてはね」と昔々から人生のベテランたちが思ってきたので、そうなっているのです。それは貯金や保険と同じで、いつ必要になるかわからないけれど、ある日、「ああ、勉強しておいてよかった」と痛感するものなのです。あるいはたとえ痛感せずとも、知らないうちにあなたの知性や思考の肥やしになっているのです。
みなさんはこれまで、論理的に考えたり表現したりすることが大事だと習ってきたはずです。けれど、大学ではその先に進まなければなりません。ひとつの問題をめぐって、こういう論理、ああいう論理、いろいろな論理を立てることができるでしょう。そのどれがベター、あるいはベストなのか。判断するためには、さまざまな視点から考える能力や想像力が必要なのです。できるだけ多くの視点を獲得する、それが大学で種々のジャンルを学ぶことの大事な意味であり、〈教養〉ということです。
ひとつの視点で主張を続ければ、一種の狂信者になってしまう危険もあります。「これはこういうものだ」と石頭になって決めつけてはなりません。学問の世界では、「真実」は常にアップデートされています。どんなに偉い学者の考えも、次の時代にはひっくり返されてしまうことが頻繁に起きるのです。神様、王様という価値判断の絶対的基準が否定された現代を生きる私たちは、「この〈正しさ〉も、いつか否定されるかもしれない相対的なものなのだ」と意識し続けるほかないのです。
私の授業ではさまざまな文学作品を読みますが、有名な作品について思いもよらない解釈が飛び出す可能性が常に存在します。たとえば、みなさんも読んだかもしれない『吾輩は猫である』や『こころ』、あれは実は...。カフカの『変身』は、わけがわからない不条理な作品とされていますが、いやいや本当はものすごくリアルで...。カミュの『異邦人』はすばらしい作品だけど、著者も意識していない差別が表れてしまっていて...。ヘッセの『車輪の下』の主人公があんなになってしまった訳は...。私が理解していることをお話しします。おもしろいはずです。けれども、もしかしたら議論の最中にもっと新しい解釈、もっと新しい〈正しさ〉を思いつくのは、あなたか
もしれません。

法学部 専任講師(化学)
土居 志織
皆さんは虹を追いかけたことがありますか ? 私は愛媛県のすごく田舎の出身ですが、実際に山の入り口まで虹を追いかけてみたことがあります。当然追いつけませんでしたが...。そんなの当たり前でしょう、と普通は思いますよね。でも「なぜ ? 」虹に追いつくことはできないのでしょう ? なぜ虹は雨上がりにしか見られないのでしょう ? なぜ虹は7色なのでしょう ? 正確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。この地球はたくさんの「なぜ ? 」に溢れています。虹を7色と定義したのはニュートンと言われていますが、ニュートンはプリズムと呼ばれる三角柱のガラスを用いて太陽光を分解すると、7色の虹の光に分かれることを発見しました。太陽光は一見、無色透明ですが、実際には目に見えない紫外線や赤外線等も含めて様々な波長の光が含まれています。虹は特別な条件が揃わないと見ることはできませんが、実は、私たちは常に虹の光の中に存在しているのです。
日常生活の中でふと「なぜ ?」と思うことはたくさんあるのに、それを受け流してしまうことは多くあります。そんな一見些細に思われる「なぜ ?」を追究してきたのがニュートンのような研究者たちです。彼らによってこれまでの長い歴史の中で様々な発見がなされ、社会、文化の成熟とともに科学も発展していきました。昨今大きな環境問題となっているプラスチックですが、開発された当初は象牙を目的とした象の乱獲を防ぐため、つまり環境を守るために開発されたものでした。それが第二次世界大戦への需要、そして現在では生活の利便性への需要へとその開発の目的は大きく変遷していきました。「科学」は発見・開発された段階で、その結果を予測するのは
困難です。つまり、私たち一人一人が「科学」を知り、正しく利用していく必要があるのです。
ところで、皆さんはご自身の代謝が良い方だと思いますか ?代謝が良い、とはどういうことなのでしょうか ? 私たちの体は60兆個もの細胞からなり、それら全てで常に様々な化学反応が行われています。これを「代謝」と言います。つまり、虹を美しいと感じること、食事を美味しいと感じることもまた、生体内の化学反応によるものです。化学は実験室で行うものだけではありません。私たち自身がまさに化学反応の場そのものなのです。大学では是非様々な科目にチャレンジしてみてください。多様な視点を持つことは、社会で役立つだけでなく、あなたの人生をより豊かにしてくれることでしょう。そして時には、ふと心に浮かんだ「なぜ ?」に耳を傾けてみて
ください。

法学部 教授(フランス語)
大出 敦
法学部で外国語を学ぶとは?
みなさんは漠然と大学に入学すると1,2年次は外国語学習が必修だと思っているでしょう。もちろんそれは間違いではなく、法学部では英独仏中西露朝の7言語の中から2言語を選択し学習します。多くの学生は英語ともう一つの言語を選択しますが、中には英語以外の言語を二つ選択する人もいます。でも改めて考えてみましょう。なぜ法学部で外国語を学習するのでしょうか。グローバル化に向けてでしょうか。海外旅行のためでしょうか。就職に有利になるためでしょうか。
法学部的感性を養う語学
言語はそれを用いる人の思考や行動を規定します。例えば「迎えに行く」という表現は、英語ではpick upですね。私が教えているフランス語ではchercherという動詞を使うのが普通です。pick upは日本語に直訳すると、「拾い上げる」「つまみ上げる」です。chercherは「探す」です。迎えに行くという行為を英語は拾い上げる行為で表現し、フランス語は探すという行為で表現しています。行為自体は同じなのにです。つまり同じ行為でも言語によって表現の仕方が異なるのです。何だ、当たり前じゃないかというかもしれませんが、この言語による物事の捉え方の違いが、自分たちと異なる考え方を生み出し、行動を規定しているのです。さらにいえば、この異質なものである言語がその国独特の法体系や政治思想の規範そのものなのです。大学での外国語学習は、結果として留学や就職に役立つかもしれませんが、実は異質な考え方を体験することで、自分たちとは異なる法体系や政治思想、社会、文化を理解する基礎学習なのです。一見したところ、専門の授業と直結しているように見えませんが、言語の習得は法学部的感性を養うものなのです。 そのため法学部では、外国語を深く学びたいと希望する学生のための週4回のインテンシヴ・コースなどみなさんのニーズに応じたさまざまなレベルのクラスを用意しています。また各言語と連動した地域文化論という特色ある授業もあります。さあ、では4月から一緒に法学部的感性を育みましょう。

法学部 教授(ロシア語)
熊野谷 葉子
法学部は2種類の外国語を学ぶ
ロシア語で「教育」は≪образование(オブラザヴァーニエ)≫と言い、「形成」と同じ言葉です。教育とは人間を形成する過程である、というこの考え方からすると、高校までのオブラザヴァーニエは教え育んでもらった第一段階、大学は自らを形成する第二段階と言えるでしょう。自分で専攻を選び、授業を選んで自己をかたちづくる、大学はそういう場です。
ところがそこに、必修科目としての外国語が控えています。法学部では2種の外国語を少なくとも週2回ずつ、2年間学びます。
語学学習は体験そのものを楽しんで
ですが、正直なところこの時間数で初習外国語の優れた使い手になることは困難ですし、単位を取り終えて勉強をやめれば文法も単語もたちまち忘れてしまうもの。まして将来使う可能性の低そうな外国語(たとえばロシア語??)の学習が、いったい何の役に立つのでしょう。
と、思いながらぼんやり授業に出ていると、授業の時間は無駄に過ぎ、宿題とテスト勉強には余計に時間がかかります。それよりも、「Жって変な字!」「格変化が6つ?ありえない...」「ボルシチってそれで赤いのか―!」といちいち大騒ぎしながら(教室で騒げという意味ではなく)、語学学習の体験そのものを楽しんでください。単語は後で忘れてしまっても、外国語とその文化に触れた記憶は貴重な財産ですし、社交辞令が言える、辞書があれば読み書きできる、というのは素晴らしい能力です。もちろん当該言語圏の文化や考え方を知って視野を拡げるのが重要なのは、言うまでもありません。
法学部にはさらに、ひとつの語学を週4回学び、4年生まで継続して鍛えられるインテンシブコースもあります。地域研究を専門にする人、外交や貿易のかけはしになりたい人のために、基礎となる語学面をサポートし続けるのも、私たち教員の仕事です。

法学部 教授(中国語)
林 秀光
1年生のうちに一生ものの発音を
4月は出会いの季節です。初めてのクラスに足を踏み入れるとき、いつも心によぎる思いがあります。なにかのご縁で、これから一緒に中国語を勉強するのだな、と。1年生から4年生までわたしのクラスに在籍する学生もいますが、就職活動を終え、一段と凛々しくなった姿に1年生の時の初々しさが思い出され、感無量の気持ちになります。
法学部中国語共通して、1年生のうちに、「一生もの」の発音を徹底的に叩き込みます。中国語の声調やきれいな響きを覚えてもらうために、わたしのクラスでは、漢詩や童謡を暗誦することもあります。2年生は他クラスの会話、読解とのバランスをとりつつ、わたしのクラスでは主として文法を系統的に勉強します。
中国語が人生を豊かにする
文法の勉強が好きな学生と苦手な学生がいますが、伸びる学生はきちんと文法も理解しているものです。わたしは、はったりはやめよう、文法を正しく自信をもって発話するようにしようと念を押しています。3、4年生になると、日吉時代にがんばった学生は目立って伸びます。それまで勉強したことを見直しつつ、さまざまな文体の中国語を読んだり、四字熟語や故事を覚えたり、中国語の「息づかい」が感じられるように、楽しんで学ぶことができます。
慶應義塾大学法学部は、日本における現代中国研究の中心としても有名です。大学で習った中国語は、学問あるいはビジネスの世界で日中関係に携わろうという君の人生を豊かにするでしょう。

法学部 教授(歴史)
片山 杜秀
無理を重ねてきた近現代の日本
広島、長崎、アウシュヴィッツ。20世紀の悲劇の舞台です。そこにチェルノブイリや21世紀に入ってからの福島を加えられるかもしれません。二つは原爆投下、二つは原発事故、一つは大虐殺。五つのうち三つまでが日本での出来事になります。
この国は世界の中でも特別に呪われているのでしょうか。まさかそんなことはありますまい。近現代の日本は、世界でも飛び抜けて背伸びしてきた。無理に無理を重ねてがんばってきた。そのせいで成功したこともいっぱいある。しかし背伸びをすれば転びやすくもなる。それゆえに悲劇の発生率も高くなる。そう考えることはできないでしょうか。
関連領域を学ぶことで見える視座
私は近現代の日本の思想や文化の歴史にとりわけ興味を持っています。具体的に言えば、二つの世界大戦の時代、さらに戦後の政治思想や社会思想、哲学や文化芸術です。そこには多くの実りがある。けれど無理をしすぎたゆえの失敗や悲劇もある。今の日本はそういう教訓を学んだり忘れたり、とにかくその積み重ねの果てに出来ている。やはり温故知新です。歴史を振り返ってこそ初めて今を学ぶ視座も獲得できるというものでしょう。 みなさんは法律や政治に興味を抱かれて法学部を目指されるのだと思います。しかしそれだけをいきなり極めるということは、当たり前ですがありえません。前提や関連領域をよく知ってこそ初めて見えて気づいて閃くことも多い。歴史を含めた人文科学の諸講座は、そのために用意されているのです。
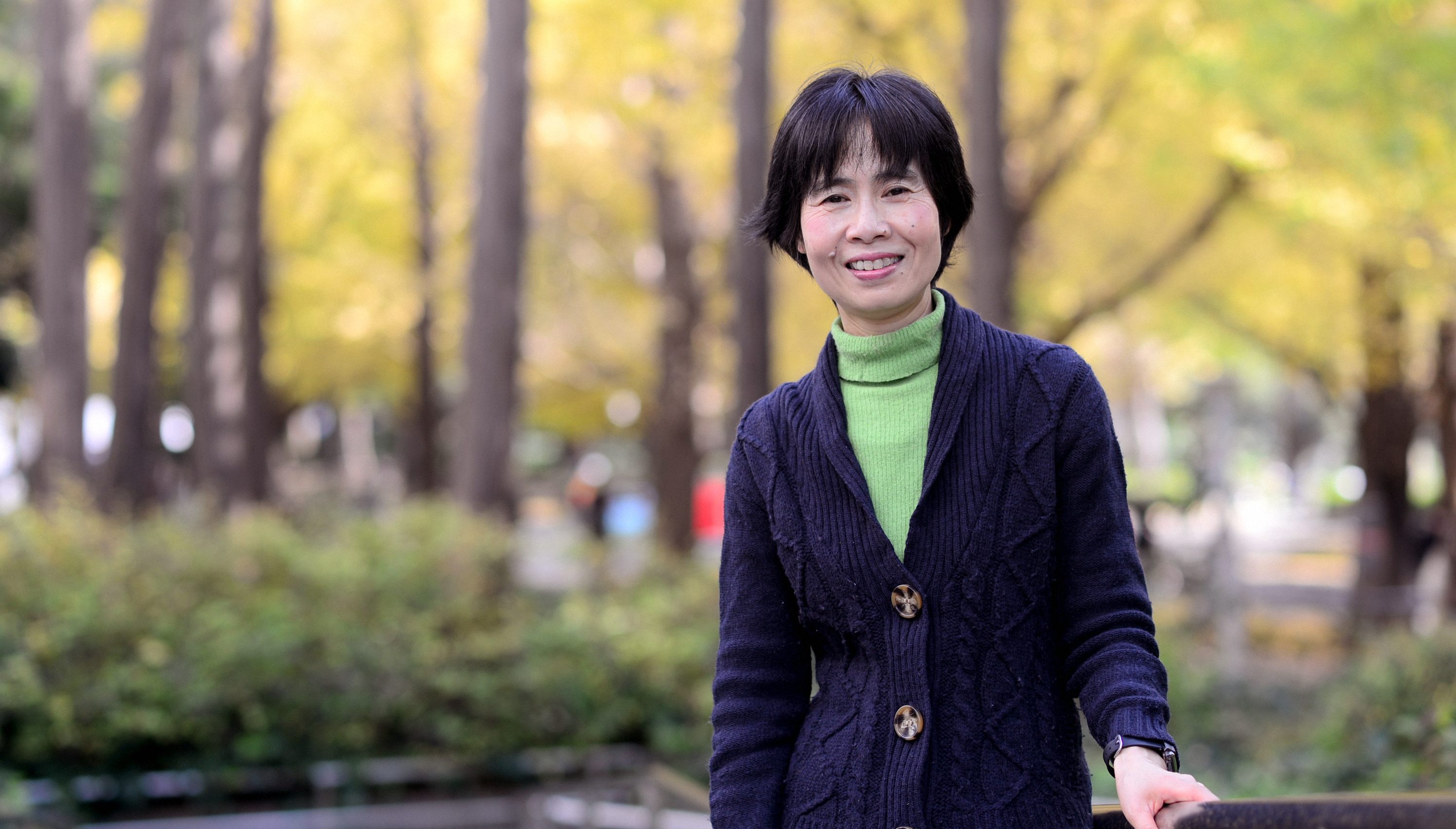
法学部 教授(英語)
横山 千晶
2020年に新型コロナウィルスは私たちの日常と価値観を根底から覆しました。ウィルスは高齢者や少数民族の人々、有色人種など、弱者やマイノリティといわれてきた人々を真っ先に襲ったことで、私たちがコミュニティと呼ぶものの暗部に光を当てました。この社会的不平等は、アメリカで起こったBLM運動と結びつき、世界的な運動を引き起こしました。アフリカ系アメリカ人に対する暴力と差別は、奴隷貿易と植民地支配という同じ人間の搾取の歴史に由来するからです。
また当然のように享受していた文化的な活動がストップした際に、いち早くアーティストの緊急支援を行ったのがドイツでした。3月23日にグリュッターズ文化相の次の言葉を受けて、芸術家を含む自営業者への6兆円の緊急支援が発表されました。「アーティストは、今、生命維持に必要不可欠な存在だ。」イギリスも3月24日に、最初の芸術救済資金、216億円の投入に踏み切りました。日本では、文化庁が支援策を発表したのがようやく7月6日のこと。多額の560億円が用意されたとはいえ、申告の複雑さや使い勝手の悪さは、当事者の目線に立っているとは言い難いものでした。
このような社会問題や意識の違いはCOVID-19が作り出したものではありません。歴史の中で培われてきたものが、今回のパンデミックで顕在化したのです。
そして、ウィルスはこの長い歴史の中で何度も人間を襲い、人々はウィルスとの共存の道を探ってきました。人間もウィルスも自然の一部です。ウィルスとの共存は、人間のレジリアンス(強靭さ)の精神と新たな文化を生み出してきました。
私の専門は19世紀のイギリス文化ですが、19世紀は現在と切り離されてはいませんし、イギリスの歴史から日本にいる私たちが学べることはたくさんあります。そして今ここに生きていることそのものが、過去を引き継ぎ世界に向けての歴史を創り出しているのです。パンデミックの時代だからこそ、未来のために私たちが遺せることはたくさんありそうです。

法学部 教授(朝鮮語)
礒﨑 敦仁
慶應法学部の東アジア研究には伝統があり、多くの研究者を輩出してきました。私はその傍流で、北朝鮮政治を専門にしています。
入手可能な情報に制限がある国家を研究対象にするには、間接的な手掛かりを相互補完的に活用することが必要になります。フィールドワークは不可能ではないものの、自由に歩き回ったりインタビューしたりすることはできません。韓国に亡命した脱北者の話はバイアスがかかっていることもあり、聴取は慎重に進めます。関係国の資料を収集するためにソウル、北京、ワシントン、モスクワなどに足を延ばすこともしばしばです。
しかし、最も頼りになるのは、北朝鮮自身が発信する公開情報の分析だと言えば意外に思うでしょうか。平壌で発行される新聞の論調はいかなるものか、そこに特定の語彙が何回出現しているか、最高指導者に随行する人物の顔ぶれに変化はないか、などを綿密に読み解いていきます。この手法は、ソ連分析で伝統的に行われてきたクレムリノロジーを文字って「ピョンヤノロジー」などと称すべきものです。限界はあるものの、彼らの論理やビジョンを読み解くには有効です。
福澤諭吉先生は、アジア諸国も近代化して独立を果たすべきだとして、朝鮮半島からの留学生を慶應義塾に招き入れました。明治14年のことです。隣国とは衝突も多いですが、感情論に流されず建設的な議論を進めることが重要です。未来を担う皆さんが良き伝統の継承者となることを切に願います。
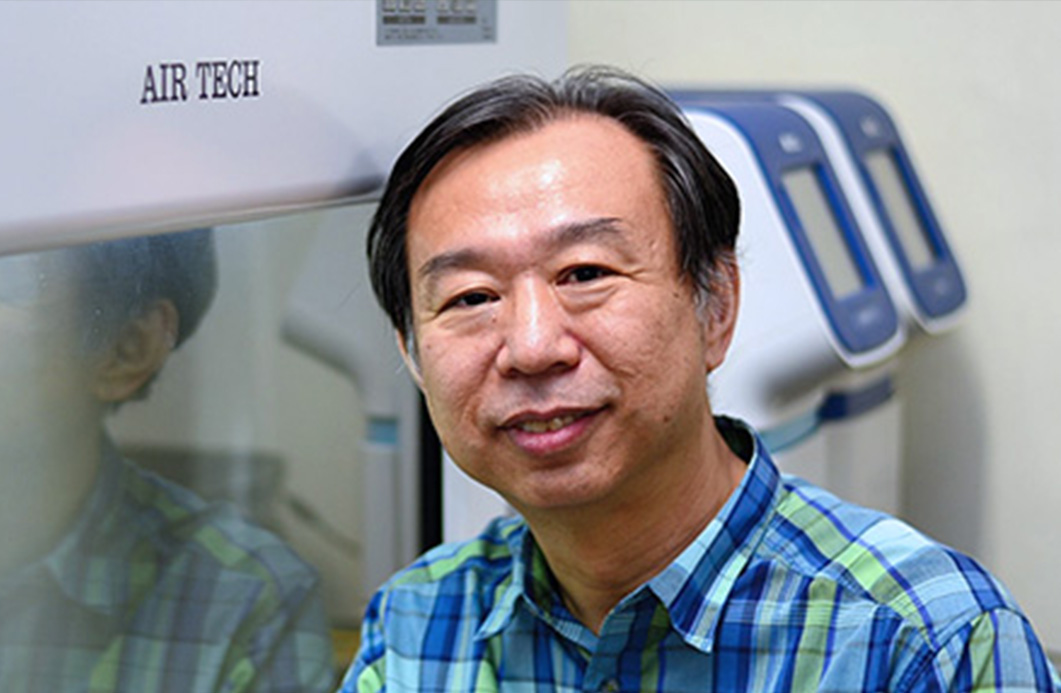
法学部 准教授(生物学)
小野 裕剛
社会問題と密接なかかわりを持つ生物学
「法学部なのに自然科学?」と聞かれることもありますが、法律や政治の対象となるのがヒトという生物の活動である以上、科学的観点を避けることはできません。とはいえ、基礎的な内容だけでは眠くなるばかりですから、私のクラスでは「民間の遺伝子検査の問題点と規制のあり方」とか「感染症と公衆衛生行政の問題点」といった社会問題と関連づけながら、問題解決に必要な知見について分子生物学を中心に解説しています。法学部に学ぶ皆さんが科学的内容を含めて問題点を正しく理解し、的確な判断力によって上手な社会的合意点を見つけてくれることを期待しています。
ロールプレイング形式で表現力を鍛える
自然科学科目にはもう一つの目的があります。福澤諭吉先生は『物理学之要用』の中で「初学を導くに専ら物理学を以ってして、恰も諸課の予備となす」と述べられ、自然科学の持つ論理性が全ての学問の基礎となることを示唆されています。日吉キャンパスでは文系学生向けに【実験を含む】科目を大規模に設置しており、これらの科目こそ、実験結果を論理的に検証し、レポートを作成する過程を通じて「諸課の予備となす」ための科目なのです。 私のクラスでは表現力をより鍛えるために、自らを企業の研究員や医師であると仮定してクライアントに対して研究開発や医学検査の意義を説明する、いわゆる"ロールプレイング形式"での課題設定を行っています。

法学部 准教授(化学)
志村 正
自然科学の重要性
慶應義塾という名が生まれた1868年、福澤諭吉先生は、『訓蒙 窮理図解(きんもう きゅうりずかい)』という日本で最初の科学入門書を著しました。先生は、日本人のほとんどが科学的な思考力をもっていないこと、つまり日本固有の文明そのものが窮理学(物理学)の原則を欠いていることに危機感を抱き、この本をはじめ、再三にわたって自然科学の重要性を説いてきました。しかし残念ながら、150年経った今でも、我が国の理科離れ傾向に変わりはありません。その一因として、高校までの理科や数学の授業では、理論が組み立てられていく途中経過や根本となる原理にまで深く踏み込んだ教育をする時間がなく、自然科学の面白さを十分に伝えられていないことがあげられます。
法学部の自然科学
法律学や政治学が成立してきた過程では、自然科学的な思考法が大きな役割を果たしています。法学部でこれらの社会科学を専攻することになる皆さんにとって、自然科学の細かい知識を得ることは、さほど重要ではないかも知れません。むしろ物事を疑ってかかり、論理的に考察して、その理由を理解したうえで原理や法則を導いていくといった自然科学的な思考力を身につけることが大切です。法学部では、講義と実験を半分ずつ行う物理学、化学、生物学といった実験科目、心理学、数学、統計学、特論や総合講座など多くの科目を履修できるように用意しています。自然科学は、決して公式や法則の暗記科目ではありません。大学で本来の自然科学を存分に楽しみ、科学する力と心を養いましょう。
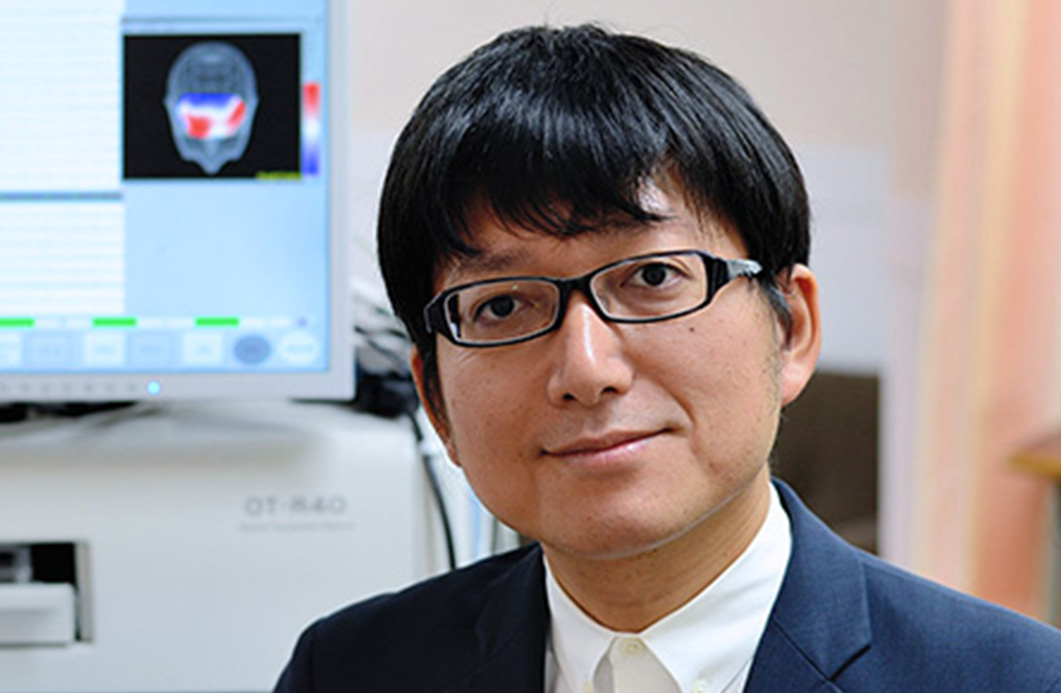
法学部 準教授(心理学)
田谷 修一郎
私の専門は心理学です。特に人が世界を認識する仕組みと、そこに由来する人間の誤りについて興味を持っています。
感覚器官の性質や行動範囲の限界等のため、私達の得ることができる世界の情報はとても狭く限られています。それに対し私達は欠けた情報を補って世界を認識する仕組みを備えています。例えば世界は高さと幅と奥行きからなる三次元空間ですが、目に映る世界は奥行きの欠けた二次元像です。私達はこの欠けた次元を補い、世界を三次元空間として認識することができます。しかしそうして次元をひとつ繰り上げて知覚され意識に上る物の形や大きさは、元の二次元像とはズレたものとなることが珍しくありません。このことは様々な錯視(目の錯覚)の原因のひとつと考えられています。
欠けた情報を補う心の働きが世界の誤った認識をもたらす例は錯視に限りません。例えば、私達は自分のよく目にするものほどたくさんあると単純に思い込む強いクセを持ちます。ためしに、日本国内のコンビニエンスストアと歯科医院、美容室を、数の多い順に並べてみてください。授業でこの質問をすると、ほとんどの学生はコンビニを先頭に並べるのですが、統計を見てみると、美容室が圧倒的に多く、次いで歯科医院、最も少ないのはコンビニです。この話をすると皆とても驚きますが、そもそも店舗数の統計情報を持っている人はまずいないので、正しく答えられないのは当たり前ともいえます。むしろ興味深いのは、なぜか皆店舗数の認識にそれなりの自信を持っている(だからこそ、それが誤りであることに驚く)ということです。このことは、いかに私達が限られた情報から「世界とはおおよそこのようなものだ」という強い、そしてときに誤った信念を形作るかを示しています。多様な情報に容易にアクセス可能となった結果その取捨選択の必要に迫られる昨今、私達が世界を認識する仕組みとその誤りを知ることの重要性は高まっていると考えます。
