- ホーム
- 法律学科
- 研究会(ゼミナール)一覧
研究会(ゼミナール)一覧
研究会(ゼミナール)一覧
公法 |
石塚壮太郎(憲法)、駒村圭吾(憲法)、小山剛(憲法)、山本龍彦(憲法)、山元 一(憲法)、横大道聡(憲法) |
|---|---|
青木淳一(行政法)、磯部 哲(行政法)、漆 さき(租税法)、戸部真澄(環境法) |
|
武井良修(国際法)、竹内 悠(宇宙法)、尹 仁河(国際法) |
|
刑事法 |
太田達也(刑事政策)、亀井源太郎(刑法・刑事訴訟法)、小池信太郎(刑法)、佐藤隆之(刑事訴訟法)、佐藤拓磨(刑法)、フィリップ・オステン(国際刑事法)、薮中 悠(刑法) |
民事法 |
麻生 典(知的財産法)、岩川隆嗣(民法)、北澤安紀(国際私法)、君嶋祐子(知的財産法)、髙 秀成 (民法)、田髙寛貴(民法)、平野秀文(民法)、松尾 弘(民法)、丸山絵美子(民法)、武川幸嗣(民法) |
商法 |
久保田安彦(商法)、杉田貴洋(商法)、鈴木千佳子(商法)、高田晴仁(商法)、松元暢子(商法)、南 健悟(商法)、柳明昌(商法) |
民事手続法 |
大濱しのぶ(民事訴訟法)、川嶋隆憲(民事訴訟法)、金 美紗(民事訴訟法) |
社会法 |
石岡克哉(経済法)、林 健太郎(労働法)、渕川和彦(経済法) |
基礎法・外国法 |
岩谷十郎(日本法制史)、大屋雄裕(法哲学)、佐伯昌彦(法社会学)、出口雄一(日本法制史)、前田美千代(ラテンアメリカ法)、薮本将典(西洋法制史) |
研究会紹介
君嶋 祐子 研究会
〈知的財産法〉

知的財産は、知的創作や商標などの無体物のうち、人の知能的活動、事業活動の成果として財産的価値のあるものの総称です。知的財産法は、知的財産の保護と利活用について規律する法分野であり、特許法、著作権法、商標法、不正競争防止法など、多くの実定法を含みます。
君嶋ゼミでは、3年生は特許法、著作権法などの判例研究を中心に行い、ソクラテスメソッド、すなわち質疑応答や討論を通じて、知的財産法の基礎の修得を行います。4年生は、知的財産法分野からテーマを選び、大学院生との合同ゼミで中間発表を行ったうえで、約1年かけて卒業論文を完成します。判例など大量の資料から必要な情報を調べてまとめる力、意見の異なる他者と話し合って新たな視点や問題解決策を見出す力を養います。
卒業生は、企業や官公庁のさまざまな業種で活躍し、また、弁護士や研究者など専門職に就く者、出産育児などを経てキャリアに復帰する者もいます。卒業後直ちに大学院に進学する者や、社会人の経験を経てから大学院進学や留学をし、キャリアアップや変更をする者もいます。
研究対象のためか、小説、絵画、音楽、漫画、アニメ、映画、演劇、ダンス、プログラミング、ゲーム、メタバース、国際関係、そしてもちろん法律学など、さまざまな興味や特技を持った学生が集まる君嶋ゼミは、在学中はもとより、卒業後もOBOG会などで交流でき、教員も含めて互いに教え学び合う半学半教のコミュニティです。


武井 良修 研究会
〈国際法〉

ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルとパレスチナの間の紛争をはじめとして、最近の報道においては国際法への言及がなされることが以前より格段に多くなりました。また、国際法が規律する事項は、現在では環境、経済、航空、宇宙、そしてサイバー空間にまで広がっており、知らず知らずのうちに国際法のルールが実は皆さんの生活に影響を及ぼしている場合も多いです。国や国際機構だけでなく個人、NGO、企業なども重要なアクターとして国際法の形成・実施に関与するようになっており、国際法は以前にもまして我々の生活に密接に関わるようになっています。
本研究会では、3年次には文献講読、判例研究、模擬裁判などを通じて国際法の理解を深め、4年次には卒業論文の執筆に向けた研究を進めています。また、春と夏の合宿を通じて、ゼミ生同士で集中的に国際法について議論する場を設けています。これに加え、国際法を理解するのには、単に文書に書かれた情報を目にするだけでは十分ではないことから、ゼミでは、国際法の実務に携わっているゲスト・スピーカーによる講演、大使館訪問や国際法関連施設の見学などを通して、生きた国際法に触れることを目指しています。これらの経験を通じてゼミ生には、誤情報・偽情報に惑わされず自分の頭で判断して行動する人間として成長し、国際社会に羽ばたいていってほしいと願っています。


松元 暢子 研究会
〈商法〉

私たちのゼミ(研究会)では、主に会社法や金融商品取引法という法律を勉強しています。実際のビジネスとも関連の深い法律です。例えば、会社法は、会社の組織の仕組み(ガバナンス)、会社が資金を調達したくなった場合の手法(ファイナンス)、会社が合併したり、ある部門をその会社から切り離したりする場合の手法(組織再編)について定めています。
ゼミでは、会社法英語文献講読と、実在の会社を検討対象とした企業事例研究を行います。両方に共通するのは、「使う」という側面です。高校生までの勉強では、英語は主に「学ぶ」対象だったかもしれません。しかし、ここでは、海外の会社法の仕組みを知り、それを日本の制度と比較分析するために英語を「使って」います。また、企業事例研究では、会社法や金融商品取引法といった法律が実際にビジネスの世界でどのように「使われて」いるのかを勉強しています。法律については、「使っ
て」いく、あるいは「使う」ことを想定した分析を行う中で、制度の問題点や不備に気づき、法律の改善提案に結び付くということもあるかもしれません。
慶應義塾大学法学部法律学科のゼミは、3年生・4年生の2年間継続して履修する点に大きな特徴があります。2年間の学びを通じて、更には卒業後のOBOGとしてのつながりを通じて、ご自分の大切な居場所をひとつ増やしてほしいと思います。


田髙 寛貴 研究会
〈民法〉

売買、賃貸、損害賠償、結婚、相続、もっと身近な例でいえば電車に乗る、ホテルに宿泊する等々、我々の日常生活のあらゆる局面を対象とし、そこで生じる紛争を解決する手立てとして作られたのが、民法です。
紛争解決のために奮闘する民法の真の姿を知り、社会のいまを体感してもらうことをめざして、このゼミでは、さまざまな裁判事例を素材として全員で討論を行っています。
複雑に利害が絡み合う事件のスジを読み解き、背景事情を含め事の真相に迫る。対立する原告と被告それぞれの言い分、あるいは、同じ事件でも異なる各審級の判決など、裁判にあらわれた多様な主張や見解を分析しつつ、ゼミ生どうし意見をぶつけあう。そうした主体的な学びから、物事を客観的、多角的に眺め、論理的に思考する「リーガルマインド」を体得してもらえたら、そして何より、合宿やスポーツ、コンパなど多彩なゼミ活動を通じて、よき友との出会いの場を提供できたら、と思っています。


柳 明昌 研究会
〈商法〉

大学の研究会は「ゼミ」とよばれます。ゼミの語源はラテン語のseminarium〈苗床〉にあります。研究活動のフィールドはできるだけ広く豊かなものとなることを心がけています。
ゼミの活動は二本柱からなっています。まず、法律学の学修に必要な判例の読み方をマスターすることです。実社会における紛争について、少なくとも対立する二つの立場から分析することを通して、物事を多角的にみることができるようになります。もう一つの柱が、現代的なテーマに関する研究です。既存の法律学の枠組みにとらわれず、現代社会の直面する新しい課題に積極的にチャレンジしてほしいと考えるからです。
ここ数年は、ICO(暗号資産による資金調達)元年といわれた当時のゼミ生から提案された暗号資産の法規制のあり方に取り組んでいます。慶應の伝統とされる教師と学生がともに教え学び合う半学半教の精神のもと、共に成長できるエキサイティングな場となっています。
先行き不透明な現代において、前途有為な学生の多様で元気な芽が育つのがささやかな楽しみです。


金 美紗 研究会
〈民事訴訟法〉

私たちのゼミでは、民事訴訟法を学んでいます。
民事訴訟は、私人間に財産上のトラブルなどが生じ、それを話し合いで解決することができない場合に利用されるものですが、民事訴訟制度がしっかりしたものでないと、様々な不都合が生じます。
たとえば、重要な証拠を提出する機会が与えられないことで、真実に反する不正な判決が下されるかもしれません。訴訟に時間がかかりすぎるという評判が立てば、訴訟を利用することに消極的な人が増え、その結果、トラブルが放置されることになるかもしれません。さらには、せっかく判決が出たのに、その結論に納得しない敗訴者が紛争を蒸し返す可能性さえあります。
こうした様々な不都合を回避し、公正かつスピーディーな方法による紛争解決ができるよう、民事訴訟制度には多くの工夫が凝らされています。
ゼミでは、教員と学生間のディスカッションを通じて、民事訴訟制度上の様々な工夫について理解を深めていきます。


駒村 圭吾 研究会
〈憲法 / 言論法〉

私のゼミは憲法のゼミです。憲法学は、自由や平等、戦争放棄に天皇、果てには国家や世界秩序までを取り扱う、とても懐の深い学問分野です。ですので、学生が期待するものも、いきおい、多種多様になります。というわけで、ご覧のとおり、大人数のゼミになりました。憲法は、どうしても抽象的な議論になりがちです。そこで、このゼミでは「裁判例」を素材にして、原告・被告に分かれ、可能な限り日常の言語で議論をすることに努めています。議論も形式ばらず、談論風発・蜂の一刺し・抱腹絶倒を旨としています。裁判例に現れた生々しい事実を土台に、裁判官という高度の法律専門職の思考方法を追究しますので、高度な法律知識も必要ですが、同時に、各学生の世界観や人生観、手持ちのとっておき情報などを爆発させ、ケンカ一歩手前まで肉薄しつつも、終わった後は好敵手としてお互いを尊重し、お酒の一杯でも酌み交わす、そういう人のつながりを大切にしています。


杉田 貴洋 研究会
〈商法〉

商法・会社法を研究対象としています。たとえば、①取締役の各別の報酬額決定を代表取締役に一任できるか、②特定の株主と対立した取締役がこれに対抗するような新株発行ができるか、というような問題は、それぞれ、①取締役の報酬は定款または株主総会決議で定めるとする会社法の規定、②新株発行は取締役会の判断で実施できるとする規定の解釈の問題になります。技術的で細かい問題のようですが、現実の社会では、実績あるワンマン社長の意向に他の取締役が逆らえないとか、経営方針をめぐって大株主と取締役が対立するといったかたちで問題となります。条文を解釈する際には、その条文がどのような理由でそうした規定となっているのか(立法趣旨)というところに遡って考えることになります。ゼミでは、商法・会社法分野のさまざまな論点・判例を取り上げて、担当者に報告してもらい、これに基づいて全員参加で議論し、一緒に考えていきます。

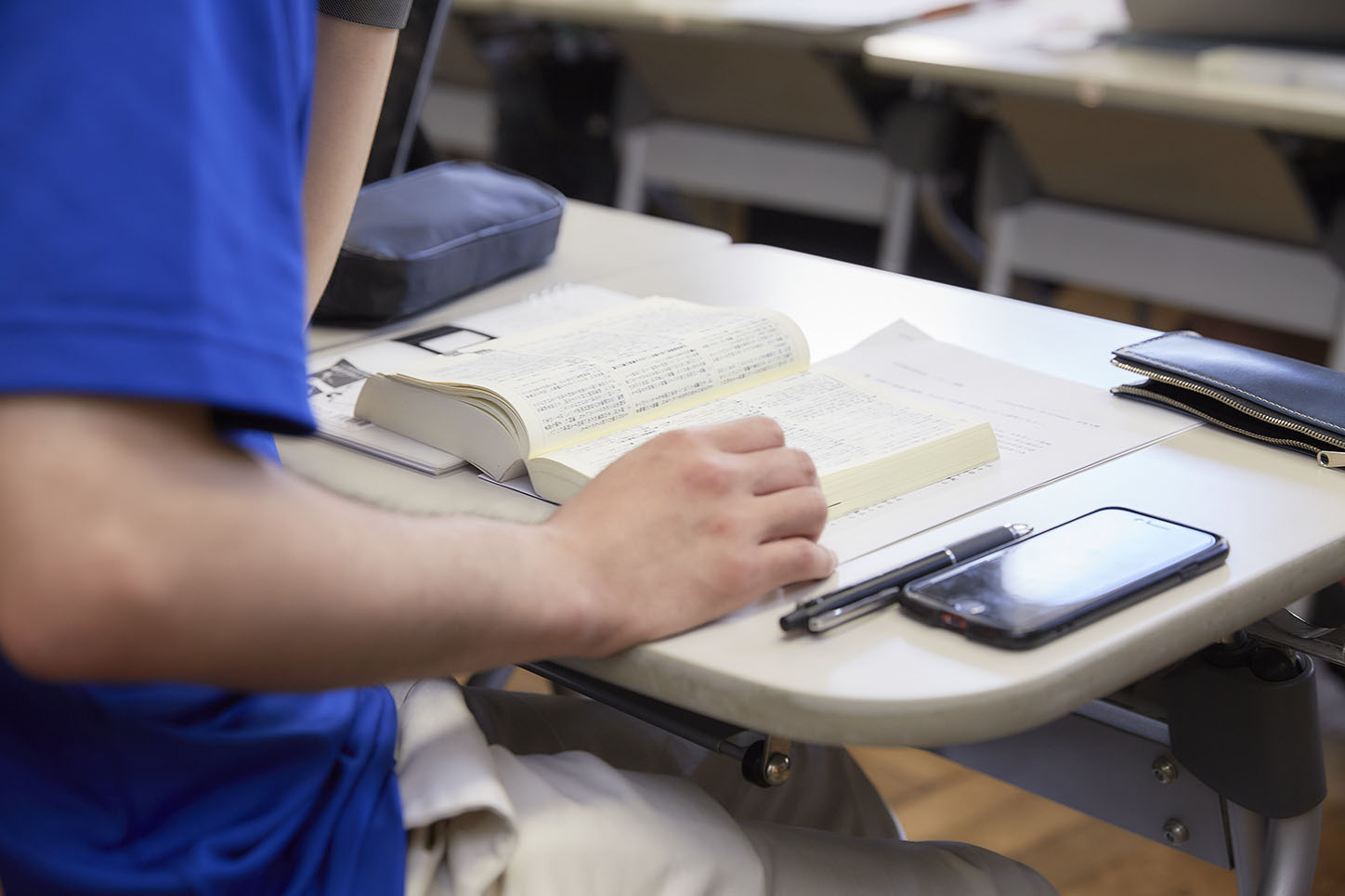

大濱 しのぶ 研究会
〈民事訴訟法 / 民事執行法〉

世の中では、借金等のお金をめぐるトラブルをはじめ、財産に関する様々な紛争が起こります。また、近年、離婚や子どものことなど家族に関する紛争も増えています。こうした紛争を民事紛争といい、解決する方法にも様々なものがありますが、このうち最も基本となるのが民事訴訟です。これは、判決という厳格な形式の裁判によって、民事紛争を解決するもので、民事訴訟法は、民事訴訟に関する手続を定める法律です。民事訴訟の理想は、裁判が適正・公平・迅速そして経済的に行われることといわれており、民事訴訟法の研究でも、こうした視点が大切です。私たちのゼミでは、民事訴訟法を、特に判例を通して勉強します。他大学の民事訴訟法ゼミとの合同ゼミにも参加しており、昨年の合同ゼミには15大学17ゼミが集まりました。ゼミは一種の共同作業で、一生を通じた友人に出会える場でもあります。みなさんも、私たちと一緒に、民事訴訟法を勉強してみませんか。


太田 達也 研究会
〈刑事司法 / 被害者学 / アジア法〉

「犯罪の少ない安全な社会」を創るにはどうしたらよいか。犯罪対策を法政策の観点から追究する学問が刑事政策学です。法学部で学ぶ法律学の99%は実定法の解釈を通じて法適用の在り方を学ぶ法解釈学であり、刑法学や刑事訴訟法学もその一つです。しかし、適正な手続に則って犯罪者に刑罰を科すだけで社会の安全が守られるわけではありません。そもそも如何なる刑罰制度を設け、どのような形で科すのがよいか、刑罰の執行過程でどのような教育や処遇を行えばよいのかを法制度の点から検討する必要があります。
当研究会では、刑務所や少年院を見学したりしながら、こうした刑事司法制度論の研究を行っています。また、今日、犯罪被害に遭った被害者の支援や刑事手続における法的地位の向上も刑事司法の重要な課題となっており、当研究会でも犯罪被害の実態や犯罪被害者への支援の在り方について研究を進めています。


小山 剛 研究会
〈憲法〉

私のゼミは、基本的人権を中心に、憲法学全般を研究しています。法律学においては、「理論」と「実践」は車の両輪です。3年次には表現の自由、生存権等の憲法上の権利について判例と学説の現状を詳細に分析する「報告」の回と、「差別的表現の規制」や「生活保護の制度後退」などの具体的事案について違憲・合憲の立場に分かれて議論する「討論」の回を組み合わせて、憲法的思考を身につけます。4年次には、議院内閣制、地方自治など統治を含めた総合演習を行うほか(春学期)、卒業研究に取り組みます(秋学期)。
学期中の勉強以外も活発です。春には新3年次生を迎えての新歓合宿、夏にはみっちり勉強となんらかの貴重な体験をする夏合宿、冬のOB・OG会など、盛りだくさんの内容です。1年たつと大人の顔に変わり、成長を実感させます。


亀井 源太郎 研究会
〈刑事法〉

本研究会は、刑法・刑事訴訟法を研究対象としています。刑法・刑事訴訟法は、いずれも、犯罪と刑罰に関する法律ですが、前者が、何が犯罪であるかを定めているのに対し、後者は、ある行為が犯罪に当たるか否か(さらに、犯罪に当たるとすればどのような刑罰を科すのがふさわしいのか)を決定するプロセスを規律する法律です。このように刑法・刑事訴訟法をともに対象とする研究会は珍しいものかもしれません。しかし、刑法上のある概念について、刑事訴訟における様々な問題を併せて考えて、はじめて、精密に理解できるという場合もあります。本研究会では、法律家を目指して勉強する学生については、刑法・刑事訴訟法の諸問題への理解を一層深めることを目指しています。また、民間企業等への就職を望む学生については、幅広い視野で物事を考える思考力と習慣を身につけることを目指しています。


前田 美千代 研究会
〈ラテンアメリカ法〉

法の成り立ちや運用は、条文解釈だけでなく、その国や地域の歴史や文化と深く関わっています。地域文化の総合的理解の下で、各国の法を考察し、比較法の視点から日本法を見つめ直そうというのが本研究会の狙いです。ラテンアメリカ諸国も日本法と同様にヨーロッパ大陸法を受け継いでいるため両者は法体系が良く似ています。英語だけでなくさまざまな外国語を使って、いろいろな国の法制度を参考に、契約、消費者、家族、スポーツ、手続などのテーマについて、日本法の改正や立法の提案を行なっています。ゼミ員には海外経験者や留学希望者が多く、卒業生も国際的な分野で活躍しています。


佐藤 拓磨 研究会
〈刑法〉

本研究会では、社会問題と密接にかかわりのある刑法上の問題を取り上げて研究しています。具体的には、臨死介助や臓器移植などの医療に関わる刑法上の問題、DVやこれに対する反撃行為などの家族内での犯罪の問題、個人の経済活動や企業活動に伴う犯罪、詐欺に代表される財産犯罪などのほか、組織犯罪対策として最近注目を集めているマネーロンダリング処罰や、犯罪者から不法収益を剥奪するための制度のあり方といったテーマについても扱っています。大教室での講義科目では言及されることのない応用的なテーマを多く含んでいますが、研究会の学生は、1、2年時の講義で身に付けた刑法の基礎知識を生かしつつ、関連判例や論文を自ら収集・調査してゼミに臨んでいます。
ゼミでは、まず、2名の報告者が、割り当てられたテーマについての基本情報の提供と論点提示を行います。これを受けて、報告者以外の学生は、いくつかの班に分かれてグループディスカッションを行います。その後、各グループがディスカッションの内容とグループの意見を発表し、全体でさらに議論を行います。扱うテーマが教科書的な正解のないものばかりであるため、学生たちは自由に意見を述べ合い、活発に議論をしています。


フィリップ・オステン 研究会
〈刑法 / 国際刑法 / 司法制度論〉

古くは東京裁判から新しきは国際刑事裁判所(ICC)まで、身近な問題では日本で轢き逃げや殺人を起こして母国に逃げ帰る外国人の犯罪まで、国際刑事法は、人の罪と罰とに関する法である刑事法を国際的な側面から考える比較的に新しい学問領域です。 日本ではゼミで国際刑事法を専門としているところは、今でも非常に少なく、実際には、2004年に発足したわがゼミが日本初の国際刑事法講座でした。当ゼミでは、これからのグローバル社会にも対応可能な素養を身につけるべく、教師と学生が一丸となって、この「未知の」領域を積極的に研究しています。


鈴木 千佳子 研究会
〈商法〉

当研究会では、会社法という、会社の運営、資金調達、合併、企業買収などに関係する法律を研究しています。人数は3年生、4年生でそれぞれ20名前後ですが、そのなかはさらに少人数の班に分かれています。学生はその週に出された課題について、班で予習を行い、それを週1回の授業に場に持ち寄って、報告・質疑応答・討論を通じて理解を深めていきます。
人から与えられた知識を得るだけでなく、協力しながらわからないことも自ら積極的に学ぶ姿勢が身につけられるように指導します。飲み会、ゼミ合宿なども、ゼミ生が積極的に企画しています。一人一人の特徴を互いがよく知って、深く、長く付き合えるところが、ゼミの素晴らしさでしょう。


