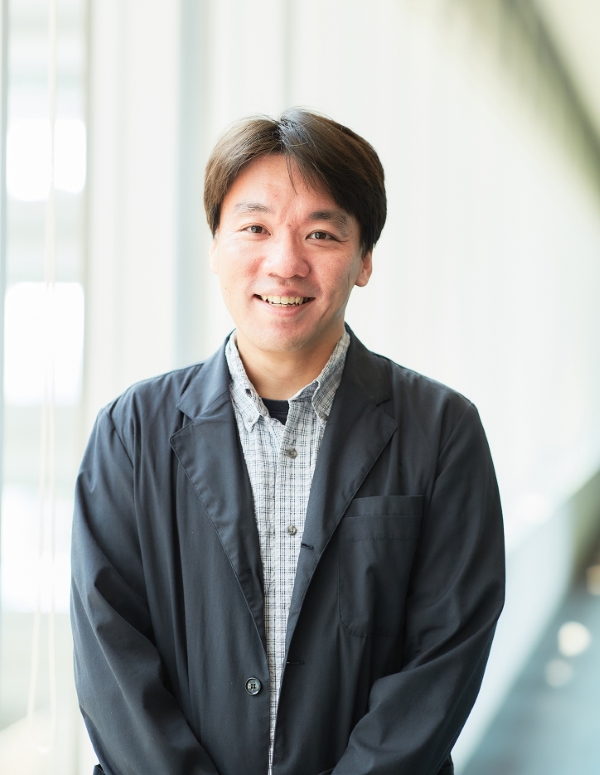
法学部専任講師
橘 宏亮
1800年頃、いわゆるゲーテ時代のドイツ文学・文化について研究しています。その中でも特に劇作家ハインリヒ・フォン・クライスト(1777~1811)の作品に集中的に取り組んできました。クライスト作品における戦争や自然災害の描写に衝撃を受けたというのがその理由ですが、クライストが死とか破壊を描くとき、そこでは、例えば次のような、今日においても重要な政治的・法的問題が同時に意識されています。
政治的表象
多くの人がその存在を信じて疑わない「国家」や「国民」ですが、これらの存在を経験的に(つまり、目で見たり手で触ったりして)捉えることは不可能です。「国家全体」とか「全国民」などが存在しうるのはイメージの中だけであって、だからこそ、こうした存在について考える場合、シンボルやメタファーといった表象媒体が必要不可欠となります。例えば国旗とか王の身体といったものがそれで、こうしたものは、実際には存在しない国家全体とか国民全体を代表します。こうすることで初めて、それらのシンボルを見た人々が国家とか国民の存在をイメージすることが可能となるのです。ところが、戦争や地震で生存が直接的に脅かされる瞬間にこうしたイメージは何の役にも立たない。そこで役に立つのは物理的暴力だけですが、クライストはこうした瞬間にこそ、国家が本来の姿を現すと考えているふしがあります。
敵の排除と政治的共同体
ある人々が、ひとまとめに「国民」とか「民族」といった名前で呼ばれるとすれば、それは彼らが何らかの共通の性格などを持っていると考えられているからです。例えば、人種主義的国家観においては同じ血を有する者が同胞とされ、そうでない者は敵として排除されますが、この区別によってはじめて人種的に純粋な国家という観念が成り立ちうるわけです。そもそも、敵が排除されるからこそ、国家が統一されるとも考えられるわけで、そうなると、敵は国家にとって構成的であるということにさえなってしまうのです。友と敵の区別という問題が最も前景化するのが戦争においてであるということは言うまでもないでしょう。
1800年頃のヨーロッパはいわば過渡期であって、それまでの秩序とか考え方が近代的なものへと移行していった時代でした。この頃に強調されるようになった概念で、現代の我々の考え方を規定し続けているものは数多くあって例えば人権などもそうです。しかし、現代の日本では自明のものとなってしまっているこの概念も、当時の人々にとっては全く新しいものでした。そこで彼らは自由とか権利とかいったものを徹底的に考え抜く必要に迫られたわけです。クライストもそうした人々の中の一人でした。ゲーテだってそうです。だから、これらの考察を記録した同時代のテキストを読むことは我々現代人の考え方を、もう一度、徹底的に見直すきっかけを与えてくれるのです。
