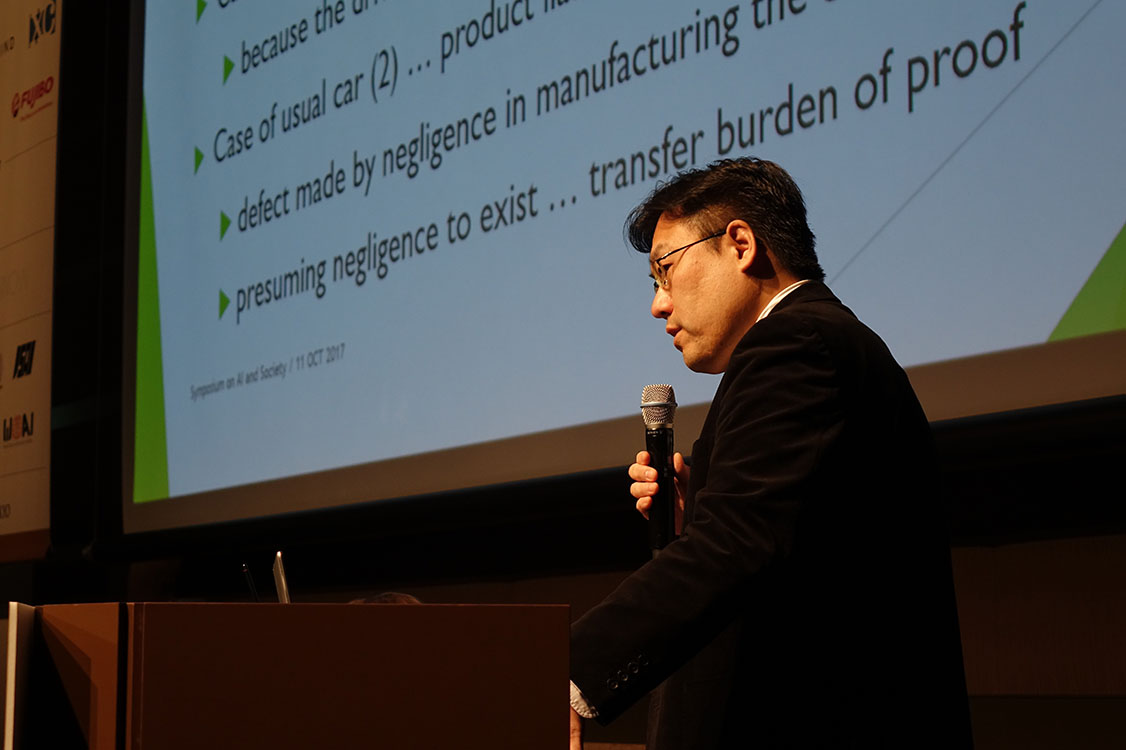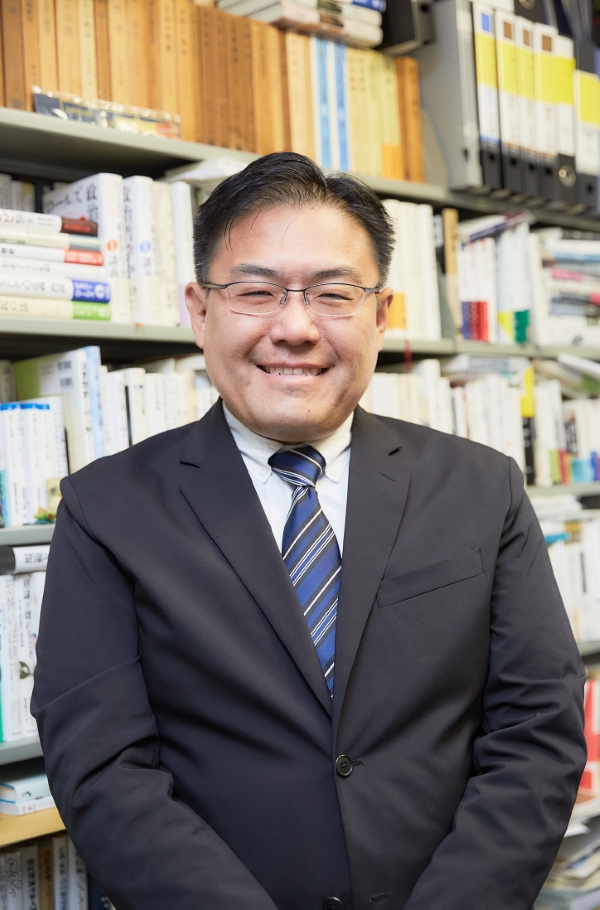
法律学科教授
大屋 雄裕
法哲学は、「現にある」法律を対象とする実定法学とは異なり、法一般を対象とする基礎法学に属し、なかでも哲学的手法を用いることで「あるべき法」を探求することを重要な目的としています。特に、所得再分配を通じて実現される福祉国家の是非をめぐる議論は、その中心を占めてきました。学部の講義「法哲学I/II」ではこの問題や国家による統治の限界と自由の保障といった伝統的な課題を中心に取り扱っています。
私自身の研究はそれとややことなり、急速に発展する情報技術が法・政治システムに与える影響を主な対象としています。インターネットの普及やSNSの登場といった時代には、それらが流通する情報をコントロールする国家の統治能力低下をもたらすとか、その設計によって人々が為し得る行為・為し得ない行為が決められてしまうためプラットフォーム事業者の権力性が増すといった指摘をしてきました。

その観点からすると、近年の中心は人工知能(AI)の発展ということになります。たとえばAIに大学入試の採点をさせるのは許されるか許されないか、許されないとすればそれはなぜなのか。現在のようなAIの登場はほとんど予測されていませんでしたから、現にある法のほとんどはその存在を想定していません。そのような状況で、どのような規制が必要か・正当化されるかといった問題を考えるためには、我々自身がどのような社会を正義にかなっているものと考えそのなかで生きることを望むかという法哲学的な観点が欠かせません。私自身もそのような立場から、「人間中心のAI社会原則」の策定など政府による検討にも加わってきました。
さらに現在では、人間と同等の自律性と汎用性を備えた「汎用人工知能」(AGI)の誕生すら数十年以内に予測される状況になっています。それが実現し、回復不能な被害を人類社会に与えてから対策としての立法を考えはじめるのでは遅いので、いま・ここにないもの、目に見えないもののあり方を予測して対応を検討することが求められるようになっていると言えるでしょう。
変わりゆく社会のなかで適切な規制のあり方を、技術の進化とともに歩みながら構想していく能力が、これからの法律家には求められると思っています。